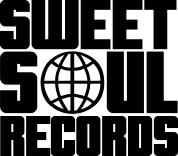3月22日(火)、代官山LOOPにて行われたNao Yoshiokaの2016年初ワンマンライブ「Nao Yoshioka Live 2016 -The Beginning of a New Chapter-」が大盛況に終わった。ソールドアウトとなったNao Yoshiokaにとって新章の幕開けをライターの林剛氏のライブレポートで振り返る。
昨年発表したセカンド・アルバム『Rising』のリード・シングル「Dreams」では“夢を追いかけるシンガー”というイメージが強調された。曲はゴードン・チェンバース作の素晴らしいバラードで、メジャー・デビューにあたってのテーマ曲のようになっていたわけだが、そうやってライヴでも夢を語るNaoの姿をいじらしいと思う一方で、メジャー・デビュー、さらには米国デビューまで果たして十分すぎるくらいに世の中にインパクトを与えた彼女に対して、夢はとっくに叶っているのでは?という思いを抱いたのも事実。夢を叶えた歌として「Dreams」を聴くこともできるけど、“夢を実現させること”が最終目標のように見えてしまっては、まだこれから先があるシンガーとしてはちょっと寂しい。やはりエンターテイナーは、夢を抱くのもいいけれど、常に皆を楽しませてくれなければ。と、そんな思いはNaoサイドにもあったのだろう。今や彼女のホームとも言える[代官山LOOP]での2016年初となるバンド・セットでのライヴのタイトルは〈Nao Yoshioka Live 2016 -The Beginning of a New Chapter-〉ということで、Nao Yoshiokaの新章を謳ったものとなった。
バックを支えるバンドのメンバーは、これまでもNaoのライヴを支えてきた面々。バンマスでベースの松田博之を筆頭に、ドラムスがFUYU、ギターが田中“Tak”拓也、キーボードが小林岳五郎、そしてコーラスがLynと吉岡悠歩という、現・日本屈指の若手ミュージシャン/シンガー6名がNaoの歌を支える。Naoのバック演奏者としては、ほとんどチームと言っていい小林岳五郎と豊田稔(パーカッション)とのトリオ編成も一体感があるし、一方で、米国ツアーをサポートし、昨年の[ブルーノート東京]公演でもバンマスを務めたフィラデルフィア在住のDai Miyazaki(宮崎大:ギター)率いるバンド、あるいはブライアン・オーウェンズのバンドも腕利き揃いで、Naoを新しい世界に導いていくような面白さがある。だが、クラブ的な空間でもある[代官山LOOP]のようなライヴ・ハウスだと、気心の知れた国内ミュージシャンの集まりである松田博之率いるバンドとの賑やかなコラボがしっくりくる。Naoも含めたメンバーが遠慮なくぶつかり合い、歌の巧さを際立たせることよりもグルーヴ重視で攻めていく心地良さは格別で、体も自然に揺れてしまう。
セットリストは結果から先に言うと8割近くがカヴァーという、アルバム・デビュー以降のフル・ステージではおそらく初の試みで、これは意外だった。「Dreams」も、CM曲として話題を集めた定番の「Spend My Life」も歌わないという、新章を謳ったライヴらしい思い切った構成だ。 オープニング曲はデビュー作からのオリジナル「I’m Not Perfect」だったものの、2曲目は、なんとアニタ・ベイカーのファースト・ソロ『The Songstress』(83年)の最後を飾っていた「Do You Believe Me」のカヴァー。オリジナルは今改めて聴くとNaoに通じる情熱的な歌が印象深いメロディアスなファンクで、これを原曲よりグルーヴィーな演奏で歌い上げた彼女は、曲を完全に自分のものにしていた。続いて歌ったのがデビュー作からのオリジナル「The Light」だったのだが、この曲といえばルーサー・ヴァンドロス「Never Too Much」(81年)を思わせるメロディ・ラインが飛び出してくるわけで、アニタの曲から続くと余計にそのメロディが際立って聞こえてくる。こうして聴き手の懐古趣味を刺激した後、MCを挿んで歌ったのがエリカ・バドゥの2003年曲「Back In The Day(Puff)」。ロイ・エアーズ・ユビキティにも通じるメロウなグルーヴに乗って歌うNaoが実に気持ちよさそうで、そのグルーヴをキープしながら、和製ネオ・ソウルとしては最高峰と断言したい出世曲「Make The Change」(作曲はバンマスの松田博之)へと続いた展開は絶妙と言うしかない。
ネオ・ソウル的な流れはここで断ち切るのかと思いきや、次にきたのがR.ケリーが書いたマックスウェルの名曲「Fortunate」(99年)。これを歌い出した時には、今回のライヴ、ちょっと様子が違うかも?と思い始めた人も多かったのではないか。マックスウェルのハイ・テナー~ファルセットが光る官能的な曲を女声でウェットに歌い上げるNao。さらに、そのムードのままマックスウェル「Ascension(Don’t Ever Wonder)」(96年)のメロディに乗せてバンド・メンバーを紹介し、メアリー・ジェーン・ガールズ「All Night Long」(83年)へとなだれ込んでいく展開には、すっかりハメられてしまった。憎らしいけど、負けた。完敗だ。と感激したのも束の間、ダメを押すかのように歌い始めたのがジャズミン・サリヴァンの「Let It Burn」(2015年)。そして、同曲のネタであるアフター7「Ready Or Not」(89年)とのベイビーフェイス(作者)繋がりということなのか、コーラスの吉岡悠歩がステージ中央に出てきて甘いテナーで歌い上げたのが、ベイビーフェイス作のジョニー・ギル「My My My」(90年)。まるで過日の〈Soul Train Awards〉のような芸の細かさである。こうした遊びも含めて、今回のテーマである〈The Beginning of a New Chapter〉の意味がおぼろげながらわかってきた。
MCを挿んだ後、ディアンジェロの「Higher」(95年)を原曲のチャーチ感全開で歌い、オーガニックなグルーヴのまま、セカンド・アルバムでもとりわけディアンジェロの世界に近かったオリジナルの「Nobody」に繋いだあたりも技アリだ。独特のズレたタイム感で音を奏でるリズム隊は(ディアンジェロのツアーをサポートした)ソウルトロニクスもしくはヴァンガードのようだ、とでも言っておこうか。デビュー作の冒頭を飾っていた「Feeling Good」(65年のニーナ・シモン版が有名)は、ベース・ソロから始まり、ファンク色強めのアレンジで。そして、「大好きなチャカ・カーンの曲です」と言って歌ったのが、ルーファス&チャカ・カーンの「Stay」(78年)。ライヴでもよく歌う「Ain’t Nobody」(83年)とともにNaoの得意とする曲で、今回のようなステージだと、より説得力をもって響いてくる。 ライヴも終盤に差し掛かった頃、かねてから予告していた“重大発表”があった。正式発表はまだ先なので、今回のステージ展開とも少なからず関係しているとだけ言っておこう(Capital Jazz Fest出演決定、ビルボードライブでの凱旋公演決定の告知のこと。現在は正式発表済み)。その発表後、ワシントンDCのローカル・ファンク=ゴー・ゴーについてNaoの口から簡単な解説があり、ジル・スコットの「It’s Love」(2000年)、自身のセカンドに収録されたオリジナル「Forget About It」というゴー・ゴー調のR&Bナンバーを二連発。最近のライヴで定番化しているこのゴー・ゴー・パートは、米国のブラック・コミュニティに接近して活動する彼女にとって大きな武器となるはずであり、また、日本では決してメジャーとは言えないゴー・ゴーという音楽を広めていくという意味でもやり続けてくれたらと思う。
今のNaoは、リアル・タイムで体験していない過去の音楽も含めて、新しい音楽を貪欲に吸収している。それをライヴのたびに披露してレパートリーの幅を広げているのだが、最近はジル・スコットの「Golden」(2004年)や「A Long Walk」(2000年)をカヴァーするなど、ジルをはじめとするフィリー産ネオ・ソウルへの憧れが強まってきているという印象を受ける。今回アンコールで歌ったマイケル・ジャクソンの「Butterflies」(2001年)も、そんな気分を象徴するものだったのではないか。フロエトリーの片割れであるマーシャ・アンブロウジアスがアンドレ・ハリスと書いたフィリー録音曲。フロエトリーのデモ版も世に出ているので、Naoはそちらを参考にしたのかもしれない。ヒラヒラと舞い上がっていく蝶のようにエレガントな美曲は、新しいチャプターに向かう今のNaoにピッタリな選曲だった。 これまでとは全く違うタイプの本気を出してきたなという印象のステージ。MCも控えめで多くを語らず、しかし、ずっと笑顔だったNaoは、ものすごく月並みな言い方になるが、本当に心から音楽を楽しんでいるというか全身で浸っているようで、微笑ましくもあり、逞しさも感じさせた。そして、オリジナル曲が少ない実験的とも言えるライヴであったにもかかわらず、お客さんの反応もいつも通り。いや、いつも以上だったかもしれない。カヴァーをやっても、キチンと筋を通していればオリジナルになるということを証明してくれた。 東京を拠点として世界を飛び回り、現地で得た人脈や体験を自身の音楽に反映させる。日本にいながら全て英語で歌い通すスタイルも含め、ほぼ前例のない活動の仕方だけに特異に映る存在ではあると思う。けれど、“こうあるべき”という無意味な常識を爽やかな笑顔でぶち破っていく姿を見ていると、彼女にはこの路線を貫いてほしいと思う。生易しくないことは承知の上で、R&Bを歌う日本のシンガーではなく、世界にいる一R&Bシンガーとして、Nao Yoshiokaの新章に期待している。
林 剛